毎朝、五十肩の痛みで目が覚めるたびに、「また今日一日が始まるのか」と憂鬱な気持ちになっていませんか。特に朝の痛みは、着替えや顔を洗うといった何気ない動作さえも辛くさせ、日常生活の質を大きく低下させてしまいます。この記事では、なぜ五十肩が朝特に痛むのか、その原因を詳しく解説するとともに、その辛い朝の痛みを根本から和らげ、安らかな眠りを取り戻すための鍼灸の有効性についてご紹介します。鍼灸は、単に痛みを抑えるだけでなく、血行促進や炎症抑制、筋肉の緊張緩和を通じて、あなたの五十肩を根本から改善へと導き、快適な朝と質の高い睡眠を叶える秘訣となるでしょう。さらに、ご自宅で実践できるセルフケアや予防法もご紹介しますので、この記事を読み終える頃には、五十肩の朝の痛みから解放され、より活動的な毎日を送るための具体的な道筋が見えてくるはずです。
1. 五十肩の朝の痛みに悩むあなたへ
毎朝、目覚めとともに肩に走る鋭い痛みや、重苦しい不快感に悩まされていませんか。五十肩の朝の痛みは、一日の始まりを憂鬱なものに変え、心身ともに大きな負担をかけるものです。特に夜間の寝返りや寝姿勢によって、朝方には肩の痛みがピークに達し、熟睡できない日々が続いている方もいらっしゃるかもしれません。
この章では、五十肩による朝の痛みがあなたの日常生活にどのような影響を与えているのか、そしてなぜ朝に痛みが強く現れるのかについて、深く掘り下げていきます。ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ読み進めてみてください。
1.1 朝の痛みがもたらす日常生活への影響
五十肩による朝の痛みは、単に「肩が痛い」というだけではありません。起床直後から感じる痛みは、その後の活動すべてに影を落とし、生活の質を著しく低下させてしまう可能性があります。具体的にどのような場面で影響を感じるか、いくつか例を挙げてみましょう。
| 影響を受ける場面 | 具体的な状況 |
|---|---|
| 着替え | 服の袖を通す動作や、下着を着用する際に腕を上げられず、痛みに顔をゆがめてしまうことがあります。 |
| 洗顔・歯磨き | 顔を洗うために腕を上げる動作や、歯磨きの際に腕を支える姿勢が辛く、満足に身支度ができないことがあります。 |
| 髪の手入れ | 髪をとかしたり、セットしたりする際に、腕が上がらず、不便を感じることがあります。 |
| 家事 | 洗濯物を干す、食器を棚に戻す、掃除機をかけるなど、腕を使う家事全般が困難になり、家族に頼むことが増えるかもしれません。 |
| 睡眠 | 夜間の寝返りや寝姿勢によって肩に負担がかかり、痛みで目が覚めたり、熟睡できなかったりすることで、疲労が蓄積しやすくなります。 |
| 精神面 | 毎朝の痛みがストレスとなり、気分が落ち込んだり、イライラしやすくなったりと、精神的な負担も大きくなります。 |
このように、五十肩の朝の痛みは、日常生活のあらゆる場面に影響を及ぼし、あなたの自由な行動を制限してしまうのです。この痛みを放置せず、適切な対処を始めることが、心身ともに健康な毎日を取り戻す第一歩となります。
1.2 「五十肩で朝痛い」と感じる原因とは
なぜ五十肩の痛みは、特に朝方に強く感じられることが多いのでしょうか。そこにはいくつかの理由が考えられます。
まず、夜間の血行不良が挙げられます。睡眠中は活動量が低下するため、肩周りの血流が滞りがちになります。血行が悪くなると、筋肉や関節に酸素や栄養が十分に届かず、老廃物が蓄積しやすくなります。これが炎症を悪化させ、痛みを増強させる原因となるのです。
次に、夜間の姿勢による肩への負担も大きな要因です。寝返りが打てなかったり、特定の姿勢で長時間寝ていたりすると、肩関節や周囲の筋肉に圧迫がかかり続けます。特に、痛い方の肩を下にして寝てしまうと、その負担はさらに大きくなり、朝起きた時に強い痛みとして現れることがあります。
さらに、筋肉の硬直も朝の痛みに深く関わっています。寝ている間、肩周りの筋肉は活動が少なく、体温も下がるため、硬くなりやすい傾向があります。硬くなった筋肉は、少しの動きでも痛みを感じやすくなり、朝起きて体を動かし始めた時に、その硬直が痛みを引き起こすのです。
これらの要因が複合的に作用することで、五十肩の痛みは朝方に最も強く感じられることが多いのです。この痛みのメカニズムを理解することは、適切な改善策を見つけるための重要な手がかりとなります。
2. 五十肩とは何か その症状と朝の痛み
五十肩は、正式には「肩関節周囲炎」と呼ばれる肩の病気です。主に40代から60代の方に多く見られ、肩関節の周りに炎症が起きることで、痛みや動きの制限が生じます。特に朝の痛みは、五十肩に悩む多くの方が経験する特徴的な症状の一つです。
2.1 五十肩の基本的な症状と進行段階
五十肩の症状は、その進行によって大きく3つの段階に分けられます。それぞれの段階で、痛みの性質や肩の動きに違いが見られます。
| 進行段階 | 主な症状と特徴 |
|---|---|
| 急性期(炎症期) | 肩に激しい痛みが生じる時期です。安静にしていてもズキズキとした痛みが続き、特に夜間や朝方に痛みが強くなる傾向があります。腕を動かすと激痛が走り、可動域が大きく制限されるため、日常生活にも支障が出やすくなります。炎症が強く、熱感を伴うこともあります。 |
| 慢性期(拘縮期) | 急性期の激しい痛みは徐々に落ち着いてきますが、肩の動きが悪くなり、固まってくる時期です。肩関節の可動域がさらに狭まり、腕を上げたり後ろに回したりすることが困難になります。痛みは動作時に感じることが多く、特に動かし始めに痛みが走ります。この時期に適切なケアを行わないと、肩の動きが元に戻りにくくなることがあります。 |
| 回復期 | 痛みも和らぎ、肩の動きが徐々に改善していく時期です。しかし、完全に可動域が元に戻るまでには時間がかかり、根気強いケアが必要です。無理な動きは避けつつ、徐々に肩を動かすことで、関節の柔軟性を取り戻していきます。この時期に適切なケアを継続することで、肩の機能が回復し、再発の予防にもつながります。 |
これらの段階はあくまで目安であり、個人の状態によって症状の現れ方や期間は異なります。ご自身の症状がどの段階にあるのかを把握することは、適切なケアを受ける上で非常に重要です。
2.2 なぜ五十肩は朝痛いのか 夜間痛との関連性
五十肩の症状の中でも、特に多くの人を悩ませるのが「朝の痛み」です。なぜ朝になると肩の痛みが強くなるのでしょうか。これは、夜間痛とも深く関連しています。
まず、夜間に眠っている間は、肩を長時間同じ姿勢で固定していることが多くなります。これにより、肩周りの血行が悪くなり、筋肉が硬直しやすくなります。血行不良は、炎症によって生じた痛み物質が滞留しやすくなる原因となり、朝目覚めたときに痛みが強く感じられるのです。
また、体温の低下も一因と考えられます。夜間から明け方にかけて体温が下がることで、血管が収縮し、肩関節周辺の血流がさらに悪化することがあります。これにより、肩の組織への酸素供給が不足し、痛みが悪化する可能性があります。
さらに、五十肩の痛みがあるために、無意識のうちに痛い肩を下にして寝ることを避けたり、寝返りの回数が減ったりすることがあります。その結果、特定の姿勢で長時間過ごすことになり、肩への負担が集中し、朝の痛みに繋がります。
夜間痛も同様に、安静時の血行不良や炎症物質の蓄積が主な原因です。寝返りを打つ際の軽い動きでも激痛が走ったり、特定の寝姿勢で痛みが強まったりすることがあります。この夜間の痛みが十分に解消されずに朝を迎えることで、「朝痛い」という感覚がより顕著になるのです。朝の痛みは、単なる寝起きの痛みではなく、夜間に肩に起こっている問題の現れと言えるでしょう。
3. 鍼灸が五十肩の朝の痛みに効果的な理由
五十肩の朝の痛みは、夜間の血行不良や炎症、筋肉の硬直が原因で起こりやすい症状です。鍼灸は、これらの痛みの根本原因に対し、多角的にアプローチすることで効果を発揮します。ここでは、鍼灸がなぜ五十肩の朝の痛みに有効なのかを詳しく解説いたします。
3.1 鍼灸が痛みの原因にアプローチするメカニズム
鍼灸は、単に痛い部分に刺激を与えるだけではありません。東洋医学の考えに基づき、全身のバランスを整えながら、痛みの根本原因に深く働きかけます。
まず、鍼の刺激は、神経系に直接作用し、痛みの信号伝達を抑制します。これにより、脳が感じる痛みの感覚を和らげることが期待できます。また、鍼刺激は、体内でエンドルフィンやエンケファリンといった自然の鎮痛物質の分泌を促進することが科学的に確認されています。これらの物質は、まるで体内のモルヒネのように働き、痛みを軽減する効果があります。
さらに、硬く緊張した筋肉や筋膜の深部にまで鍼を届かせることで、筋膜の癒着を剥がし、トリガーポイントと呼ばれる痛みの発生源を直接緩めることができます。これにより、筋肉本来の柔軟性を取り戻し、朝の動かし始めの痛みを軽減へと導きます。
3.2 血行促進と炎症抑制 鍼灸の科学的根拠
五十肩の朝の痛みには、患部の血行不良と慢性的な炎症が深く関わっています。鍼灸は、これらの問題に対して科学的な根拠に基づいたアプローチを提供します。
鍼刺激は、血管を拡張させ、患部への血流を劇的に改善します。血流が良くなることで、酸素や栄養素が効率的に供給され、損傷した組織の修復が促進されます。同時に、痛みや炎症を引き起こすプロスタグランジンなどの老廃物や発痛物質の排出も促されるため、痛みの悪循環を断ち切ることに繋がります。
また、研究により、鍼灸が炎症性サイトカインの過剰な産生を抑制し、抗炎症作用を持つ物質の分泌を促すことが示されています。これにより、五十肩で起こりがちな慢性的な炎症反応を鎮静化させ、痛みの軽減に貢献します。特に夜間から朝にかけて強くなる炎症を和らげることで、安眠を妨げる夜間痛や、目覚め時の強い痛みの緩和に役立ちます。
3.3 筋肉の緊張を和らげ可動域を改善する鍼灸
五十肩の大きな特徴の一つは、肩関節周囲の筋肉が硬くなり、動きが制限されることです。これが、朝の寝返りや腕を上げる際の痛みを引き起こす主要な原因となります。
鍼灸は、硬く緊張した肩関節周囲の筋肉や腱、そして関節包に直接アプローチし、その緊張を効率的に緩和します。特に、普段は届きにくい深層部の筋肉に対して、鍼でピンポイントに刺激を与えることで、筋肉の過緊張を解除し、柔軟性を取り戻すことができます。
これにより、肩関節の可動域が徐々に広がり、腕を上げたり、後ろに回したりといった動作がスムーズになります。朝、布団から起き上がる際や着替えをする際の痛みが軽減され、日常生活における「動かし始めの痛み」の改善に繋がります。筋肉の柔軟性が高まることで、関節への負担も減り、痛みの再発予防にも効果的です。
| 鍼灸の主な作用 | 五十肩の朝の痛みへの効果 |
|---|---|
| 鎮痛作用 | 神経伝達を抑制し、体内の鎮痛物質分泌を促進することで、痛みの感覚を和らげます。 |
| 血行促進作用 | 血管を拡張させ、患部への酸素・栄養供給を増やし、老廃物の排出を促します。 |
| 炎症抑制作用 | 炎症性物質の産生を抑え、慢性的な炎症反応を鎮静化させます。 |
| 筋緊張緩和作用 | 硬く緊張した筋肉や筋膜の深部にアプローチし、柔軟性を取り戻します。 |
| 可動域改善作用 | 筋肉の柔軟性が高まることで、肩関節の動きがスムーズになり、動作時の痛みを軽減します。 |
4. 鍼灸で五十肩の根本改善と安眠を手に入れる
五十肩による朝の痛みや夜間痛は、日常生活の質を著しく低下させ、心身ともに大きな負担となります。しかし、鍼灸は単に痛みを和らげるだけでなく、その根本原因にアプローチし、安眠を取り戻すための効果的な手段となり得ます。ここでは、鍼灸がどのようにして五十肩の根本改善と安眠をサポートするのか、具体的な施術内容や再発防止に向けた体質改善について詳しくご紹介いたします。
4.1 具体的な鍼灸施術の流れと治療計画
鍼灸による五十肩の治療は、患者様一人ひとりの症状や体質に合わせて、オーダーメイドで行われます。一般的な施術の流れは以下の通りです。
| 施術ステップ | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 1. 問診 | 現在の症状(特に朝の痛みや夜間痛の有無、程度)、痛みの始まり、過去の病歴、生活習慣、仕事内容、ストレス状況などを詳しくお伺いします。 | 五十肩の原因や症状の背景を深く理解し、個別の治療方針を立てるための重要な情報を得ます。 |
| 2. 視診・触診 | 肩関節の可動域、筋肉の緊張具合、患部の熱感や冷え、姿勢のバランスなどを確認します。関連する首や背中、腕の状態も丹念に診ていきます。 | 痛みの発生源や関連部位を特定し、鍼やお灸を施す具体的なツボや部位を決定します。 |
| 3. 鍼灸施術 | 問診と視診・触診に基づき、最適なツボ(経穴)に鍼を刺入し、またはお灸を施します。痛む部位だけでなく、全身のバランスを整えるツボも選択します。 | 血行促進、筋肉の緊張緩和、炎症抑制、神経機能の調整を図り、自然治癒力を高めます。 |
| 4. 治療計画の説明 | 施術後、症状の改善度合いや体質を考慮し、今後の治療計画(通院頻度、期間など)をご提案いたします。 | 五十肩の根本改善と再発防止に向けた具体的なロードマップを共有し、安心して治療に取り組んでいただけるようサポートします。 |
鍼灸は、その日の体調や症状の変化に合わせて柔軟に施術内容を調整できる点が特徴です。継続的な施術と計画的なアプローチにより、五十肩の痛みを軽減し、肩の動きをスムーズにすることを目指します。
4.2 安眠を妨げる夜間痛を和らげる鍼灸
五十肩の患者様にとって、朝の痛みと同様に深刻なのが夜間痛です。夜間痛は睡眠を妨げ、身体の回復を遅らせるだけでなく、精神的なストレスも増大させます。鍼灸は、この夜間痛の軽減に非常に有効な手段となり得ます。
夜間痛の原因としては、日中の活動による肩への負担の蓄積、寝返り時の圧迫、患部の血行不良や炎症などが挙げられます。鍼灸はこれらの原因に対して、次のようにアプローチします。
- 筋肉の緊張緩和:肩周りの硬くなった筋肉を緩め、寝返り時の肩への負担を軽減します。これにより、夜間の痛みで目が覚める回数を減らすことが期待できます。
- 血行促進と炎症抑制:患部とその周辺の血流を改善することで、滞っていた老廃物や炎症物質の排出を促します。これにより、炎症による痛みが和らぎます。
- 自律神経の調整:鍼灸は、心身のリラックスを促す副交感神経を優位にする作用があります。これにより、痛みの閾値が上がり、心身が落ち着くことで、より深い睡眠へと導かれます。
夜間痛が軽減され、質の良い睡眠がとれるようになると、身体の回復力が高まり、五十肩の改善がさらに促進されます。朝の痛みの軽減にも直結するため、安眠は五十肩治療において非常に重要な要素です。
4.3 五十肩の再発を防ぐための体質改善
五十肩の治療において、痛みの除去はもちろん重要ですが、根本的な体質改善を図り、再発を防ぐことも同じくらい大切です。鍼灸は、東洋医学の考え方に基づき、全身のバランスを整えることで、五十肩になりにくい身体づくりをサポートします。
東洋医学では、五十肩を単なる肩の症状として捉えるのではなく、身体全体の「気(エネルギー)」「血(血液)」「水(体液)」の流れの滞りやバランスの乱れが原因であると考えることがあります。特に、「冷え」や「血の滞り」は五十肩の発症や慢性化に深く関わっていると考えられています。
鍼灸による体質改善のアプローチは以下の通りです。
- 全身のバランス調整:肩だけでなく、全身の経絡(気の通り道)やツボを刺激することで、身体全体の「気・血・水」の流れをスムーズにします。これにより、自然治癒力が高まり、肩への負担を軽減できる身体へと変化していきます。
- 冷えの改善:お灸を用いることで、身体を内側から温め、血行を促進します。特に肩や背中の冷えは五十肩の痛みを悪化させることが多いため、冷えを改善することは再発防止に繋がります。
- ストレス緩和:ストレスは自律神経の乱れを引き起こし、筋肉の緊張や血行不良を招くことがあります。鍼灸はリラックス効果も高く、ストレスによる身体への影響を和らげ、心身のバランスを整えます。
施術と合わせて、日々の生活習慣(食事、運動、睡眠など)に関するアドバイスも行い、患者様ご自身で体質改善に取り組めるようサポートいたします。痛みが取れた後も定期的に身体のメンテナンスを行うことで、五十肩の再発を防ぎ、健やかな毎日を送るための土台を築くことができます。
5. 自宅でできる五十肩のセルフケアと予防
鍼灸治療の効果を最大限に引き出し、五十肩の朝の痛みを和らげ、再発を防ぐためには、ご自宅でのセルフケアと日々の生活習慣の見直しが非常に重要です。ここでは、朝の痛みに特化した効果的なセルフケアと予防策をご紹介いたします。
5.1 朝の痛みを軽減するストレッチと体操
朝の痛みは、睡眠中に肩周りの筋肉が硬直し、血行が悪くなることが一因です。起床後のストレッチや体操は、肩関節の柔軟性を高め、血行を促進し、痛みを和らげる助けとなります。無理のない範囲で、ゆっくりと丁寧に行うことが大切です。
5.1.1 振り子運動(コッドマン体操)
この体操は、肩関節への負担を最小限に抑えながら、肩の可動域を広げるのに役立ちます。特に朝、肩が固まっていると感じる時に有効です。
- 痛い方の腕をだらんと垂らし、体を少し前に傾けます。
- もう片方の手でテーブルや椅子の背もたれを支え、安定させます。
- 腕の重みを利用して、ゆっくりと円を描くように前後に揺らしたり、左右に振ったりします。
- 痛みを感じない範囲で、小さく始めて徐々に動きを大きくしていきます。
- 各方向へ10回程度、深呼吸をしながら行いましょう。
5.1.2 壁を使った肩甲骨ストレッチ
肩甲骨周りの筋肉をほぐすことで、肩関節の動きがスムーズになり、朝の痛みの軽減につながります。
- 壁に横向きに立ち、痛い方の腕を壁につけます。
- 手のひらを壁につけたまま、ゆっくりと腕を上に滑らせていきます。
- 肩甲骨が動くのを意識しながら、痛みを感じない高さまで上げます。
- 数秒間キープし、ゆっくりと元の位置に戻します。
- この動きを5回から10回繰り返しましょう。
5.1.3 胸郭を開くストレッチ
猫背気味の姿勢は肩への負担を増やし、朝の痛みを悪化させる可能性があります。胸郭を開くことで、姿勢の改善と肩の解放を促します。
- 両手を頭の後ろで組み、肘を大きく開きます。
- ゆっくりと息を吸いながら胸を天井方向へ持ち上げ、背中を軽く反らせます。
- 数秒間その姿勢を保ち、息を吐きながらリラックスします。
- この動作を5回程度繰り返します。
どのストレッチも、痛みを感じる手前で止めることが重要です。無理に動かすと、かえって症状を悪化させる可能性がありますので、ご自身の体の声に耳を傾けながら行いましょう。
5.2 温め方と冷やし方 適切な対処法
五十肩の痛みに対しては、症状の段階に応じて温めるか冷やすかを適切に判断することが大切です。特に朝の痛みには、血行促進が鍵となります。
| 症状の段階 | 特徴 | 対処法 | 具体的な方法 |
|---|---|---|---|
| 急性期(炎症期) | 強い痛み、熱感、腫れがある | 冷やす | 氷嚢や保冷剤をタオルで包み、患部に15~20分程度当てます。 冷湿布も有効です。 冷やしすぎないように注意し、感覚が麻痺する前に外しましょう。 |
| 慢性期(拘縮期、回復期) | 痛みが落ち着き、肩の動きが悪い、硬さを感じる | 温める | 蒸しタオルを患部に当てる(やけどに注意)。 入浴で全身を温め、肩周りの血行を促進します。 使い捨てカイロや温湿布も効果的です。 朝の痛みには、起床時に温めることで筋肉の硬直が和らぎやすくなります。 |
朝、肩の痛みで目覚めることが多い場合は、起床前に肩を温める準備をしておくことも有効です。例えば、寝る前に肩にカイロを貼る(低温やけどに注意し、直接肌に貼らない)、電気毛布で肩周りを温めるなどの工夫が考えられます。温めることで血行が促進され、硬くなった筋肉がほぐれやすくなり、動き出しの痛みが軽減されることが期待できます。
5.3 鍼灸と併用して効果を高める生活習慣
鍼灸治療の効果を最大限に引き出し、五十肩の根本改善と安眠、そして再発予防のためには、日々の生活習慣を見直すことが非常に重要です。特に朝の痛みに影響を与える要素に注目しましょう。
5.3.1 睡眠環境の改善
質の良い睡眠は、体の回復力を高め、痛みの軽減につながります。特に朝の痛みに悩む方にとって、寝姿勢や寝具は大きな影響を与えます。
- 枕の高さ:高すぎず低すぎない、首のカーブに合った枕を選びましょう。枕が合わないと、首から肩にかけての筋肉が緊張しやすくなります。
- 寝姿勢の工夫:
- 仰向けで寝る場合:痛い方の腕の下に薄いタオルなどを敷き、肩が沈み込むのを防ぐと楽になることがあります。
- 横向きで寝る場合:抱き枕を利用して、腕や肩の重みを分散させると良いでしょう。痛い方を上にして、腕を抱き枕に乗せる姿勢もおすすめです。
- 寝返りのしやすさ:寝返りは血行を促進し、同じ姿勢でいることによる体の負担を軽減します。適度な硬さのマットレスを選び、寝返りが打ちやすい環境を整えましょう。
5.3.2 姿勢の意識と改善
日常生活における姿勢は、肩への負担に直結します。特にデスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けることが多い方は注意が必要です。
- 正しい座り方:椅子に深く座り、背筋を伸ばし、肩の力を抜きましょう。パソコンのモニターは目線の高さに合わせ、キーボードやマウスは無理なく操作できる位置に置きます。
- 立ち姿勢:耳、肩、股関節、くるぶしが一直線になるようなイメージで立ちます。肩甲骨を意識して軽く引き寄せることで、胸が開き、肩への負担が軽減されます。
- 定期的な休憩:長時間同じ姿勢でいることを避け、1時間に1回程度は立ち上がって軽く体を動かしたり、ストレッチを行ったりしましょう。
5.3.3 バランスの取れた食事と水分補給
体を作る基本である食事は、炎症を抑え、組織の修復を助ける上で非常に重要です。
- 抗炎症作用のある食品:青魚に含まれるオメガ3脂肪酸(DHA、EPA)、緑黄色野菜、果物などを積極的に摂りましょう。
- タンパク質:筋肉や腱の修復に必要不可欠です。鶏むね肉、魚、大豆製品などをバランス良く摂取しましょう。
- 十分な水分補給:体の巡りを良くし、老廃物の排出を助けます。こまめに水分を摂ることを心がけましょう。
5.3.4 ストレス管理とリラックス
ストレスは筋肉の緊張を高め、痛みを悪化させる要因となります。心身のリラックスは、鍼灸治療の効果を高める上でも重要です。
- 入浴:温かいお風呂にゆっくり浸かることで、全身の血行が促進され、筋肉の緊張がほぐれます。アロマオイルなどを利用して、リラックス効果を高めるのも良いでしょう。
- 趣味や休息:好きなことに没頭する時間や、何もしない休息の時間を意識的に作り、心身を休ませましょう。
- 深呼吸:意識的に深くゆっくりと呼吸することで、自律神経のバランスを整え、リラックス効果を高めることができます。
これらのセルフケアや生活習慣の改善は、鍼灸治療と組み合わせることで、五十肩の朝の痛みの軽減はもちろん、症状の早期改善と再発予防に大きく貢献します。ご自身のペースで、できることから少しずつ取り入れてみてください。
6. まとめ
五十肩による朝の痛みは、日中の活動だけでなく、夜間の睡眠まで妨げ、日常生活に大きな影響を及ぼします。この朝の痛みの主な原因は、炎症や血行不良、筋肉の過度な緊張などが考えられます。
鍼灸は、これらの痛みの根本原因に対し、血行促進、炎症の抑制、そして硬くなった筋肉の緊張を和らげることで、効果的にアプローチします。その結果、五十肩特有の夜間痛や朝の痛みが軽減され、深い安眠と肩の可動域の改善、さらには再発しにくい体質への改善が期待できます。
また、鍼灸治療と並行して、ご自宅での適切なストレッチや温冷ケア、生活習慣の見直しを行うことで、より一層の改善と予防につながります。五十肩の朝の痛みでお悩みでしたら、ぜひ一度、鍼灸治療をご検討ください。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。
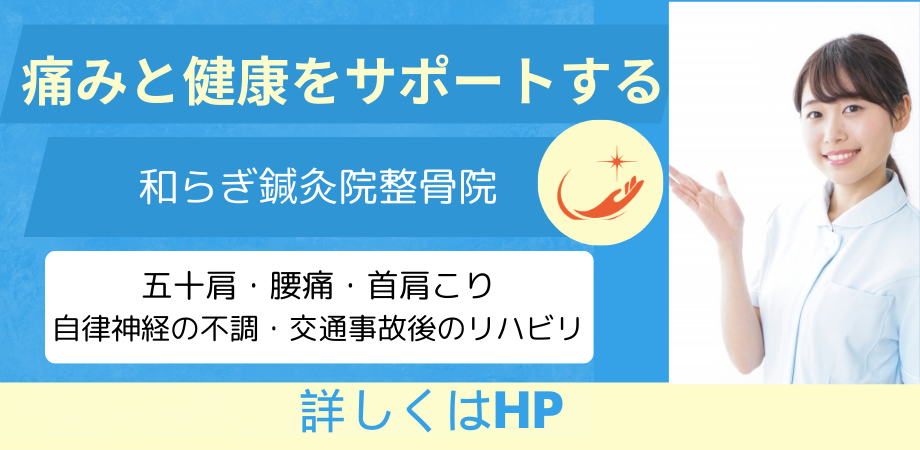














コメントを残す