右側の肩の痛みで、日常生活に支障をきたし、つらい思いをされていませんか。その痛みは、使いすぎや姿勢不良、寝違え、加齢、内臓疾患など、多岐にわたる原因が考えられます。この記事では、痛みの原因を徹底解説し、整骨院での根本改善アプローチ、施術ステップ、セルフケアまでご紹介。痛みを解消し、快適な毎日を取り戻すための具体的な方法が分かります。
1. 右側の肩の痛み どこからくる?原因徹底解説
右側の肩に感じる痛みは、日常生活での習慣や体の変化、時には意外な原因から生じることがあります。ここでは、右肩の痛みがどこから来ているのか、その主な原因を詳しく解説いたします。
1.1 右腕の使いすぎやオーバーユース
右利きの方に特に多いのが、右腕の使いすぎによる肩の痛みです。スポーツでの投球動作やラケットを振る動作、あるいは仕事で重いものを運ぶ作業、長時間のパソコン操作、家事での繰り返し動作など、右腕や右肩に過度な負担がかかり続けることで、筋肉や腱に炎症が生じたり、疲労が蓄積したりします。
特に、特定の筋肉や腱に集中して負荷がかかることで、微細な損傷が繰り返され、慢性的な痛みにつながることが少なくありません。右肩の深部に鈍い痛みを感じる場合や、腕を上げるときに特定の角度で痛みが増す場合は、使いすぎによる炎症が考えられます。
1.2 デスクワークやスマホ操作による姿勢不良
現代社会において、デスクワークやスマートフォンの長時間使用は避けられないものとなっていますが、その際に生じる姿勢の悪さが右肩の痛みの大きな原因となることがあります。特に、以下のような姿勢は右肩に大きな負担をかけます。
- 猫背:背中が丸まり、肩が前に出ることで、首や肩の筋肉が常に緊張した状態になります。
- 巻き肩:肩が内側に巻き込まれることで、胸の筋肉が硬くなり、肩甲骨の動きが制限されます。
- ストレートネック:首の生理的なカーブが失われ、頭の重さがダイレクトに首や肩にかかります。
これらの姿勢不良が続くと、右側の首から肩、背中にかけての筋肉が硬直し、血行不良を引き起こします。その結果、疲労物質が蓄積し、右肩に痛みやこりとして現れるのです。
1.3 寝違えや寝相の悪さ
朝起きたときに突然右肩や首に痛みを感じる「寝違え」も、肩の痛みの一般的な原因の一つです。これは、寝ている間に不自然な姿勢を長時間続けることによって、右側の首や肩の筋肉が過度に伸ばされたり、圧迫されたりして炎症を起こすために起こります。
特に、以下のような寝相や寝具は寝違えのリスクを高めます。
- うつ伏せで寝る
- 高すぎる、または低すぎる枕を使用する
- 体に合わないマットレスで寝る
- 寒い場所で肩を冷やしながら寝る
これらの要因により、右肩周辺の血流が悪くなり、筋肉が硬直して、翌朝の強い痛みにつながることがあります。
1.4 加齢による筋肉や関節の変化
年齢を重ねるにつれて、私たちの体は様々な変化を経験します。右肩の痛みも、加齢に伴う筋肉や関節の変化が原因となることがあります。
具体的には、以下のような変化が挙げられます。
- 筋肉量の減少と柔軟性の低下:肩を支える筋肉が衰え、柔軟性が失われることで、関節への負担が増加します。
- 腱の変性:肩の腱(特に回旋筋腱板)が加齢とともに弾力性を失い、傷つきやすくなります。これにより、腕を上げたり回したりする際に痛みが生じやすくなります。
- 関節軟骨の摩耗:肩関節の軟骨がすり減ることで、関節の動きが悪くなり、炎症や痛みを引き起こすことがあります。
これらの変化は、いわゆる「四十肩」や「五十肩」(肩関節周囲炎)と呼ばれる症状として現れることが多く、右肩の動きが制限されたり、夜間に強い痛みを感じたりすることが特徴です。
1.5 内臓疾患が原因となる関連痛
肩の痛みは、必ずしも肩自体に問題があるとは限りません。時には、体のどこか別の場所、特に内臓の不調が原因で肩に痛みを感じる「関連痛」として現れることがあります。右肩の痛みの場合、以下のような内臓疾患が関連している可能性があります。
| 関連する内臓 | 右肩に現れる関連痛の特徴 |
|---|---|
| 胆のう・肝臓 | 右肩甲骨の下あたりや右肩の前面に痛みを感じることがあります。特に食後に痛みが増す場合があります。 |
| 横隔膜(炎症や刺激) | 右側の横隔膜が刺激されると、右肩の先端部分に痛みを感じることがあります。 |
| 肺(肺炎や胸膜炎など) | 右肺に問題がある場合、右肩や首の付け根に痛みが放散することがあります。呼吸に伴って痛みが増す場合があります。 |
これらの関連痛は、肩を動かしても痛みが変わらない、発熱や吐き気、だるさなど他の症状を伴う、といった特徴が見られることがあります。いつもの肩の痛みとは違うと感じる場合や、原因がはっきりしない強い痛みが続く場合は、内臓疾患の可能性も視野に入れ、専門機関への相談を検討することが大切です。
2. 整骨院が提供する右側の肩の痛みへのアプローチ
右側の肩の痛みは、日常生活の質を大きく低下させる要因となります。整骨院では、その痛みに特化した専門的なアプローチで、症状の改善と再発予防を目指してまいります。単なる一時的な痛みの緩和だけでなく、痛みの根本原因を見極め、患者様一人ひとりに合わせた施術計画を立て、根本からの解消を目指します。
2.1 問診・視診・触診で痛みの原因を徹底究明
右側の肩の痛みは、その原因が多岐にわたるため、適切な施術を行うためには丁寧で詳細な検査が不可欠です。整骨院では、まず患者様のお話をじっくり伺う「問診」、身体の状態を目で確認する「視診」、そして直接触れて筋肉や関節の状態を把握する「触診」を徹底して行います。
これらの検査を通じて、痛みの発生時期、どのような動作で痛みが増すのか、過去の怪我や病歴、日頃の生活習慣など、右側の肩の痛みに影響を与えている可能性のある情報を詳細に収集いたします。特に右側の肩の痛みの場合、利き腕の使いすぎ、デスクワークでの姿勢、寝方、内臓からの関連痛など、様々な要因が考えられますので、多角的な視点から原因を究明することに努めます。
| 検査項目 | 目的と確認内容 |
|---|---|
| 問診 | いつから、どのような痛みがあるのか、日常生活での困りごと、過去の怪我や病歴、仕事や趣味の内容、睡眠状況など、右側の肩の痛みの背景にある情報を詳しくお伺いします。 |
| 視診 | 姿勢の歪み、肩甲骨の位置、左右のバランス、筋肉の盛り上がりや萎縮、皮膚の色や腫れの有無など、視覚的に確認できる情報をチェックし、痛みの原因の手がかりを探ります。 |
| 触診 | 右側の肩周辺の筋肉の硬さ、コリ、張り、関節の動き、熱感の有無などを直接触れて確認します。特に痛みを感じるポイントや、関連する筋肉の状態を丁寧に探ります。 |
2.1.1 筋膜リリースとトリガーポイント療法
右側の肩の痛みの原因の一つに、筋膜のねじれや癒着、あるいは筋肉内にできたトリガーポイントが挙げられます。筋膜は筋肉を包み込む膜で、全身に張り巡らされており、その柔軟性が失われると、動きが悪くなったり、痛みが生じたりすることがあります。
整骨院では、この筋膜に対して「筋膜リリース」と呼ばれる手技を用いて、ねじれや癒着を剥がし、本来の滑らかな動きを取り戻すことを目指します。これにより、右側の肩の可動域が改善され、痛みの軽減につながります。
また、筋肉の奥深くに存在する「トリガーポイント」は、押すと痛みが広がる特徴があり、右側の肩の痛みの原因となることが少なくありません。このトリガーポイントに対しては、適切な圧をかけることで、筋肉の緊張を緩和し、痛みを根本から和らげることを目的とした施術を行います。
これらの施術は、血行促進効果も期待でき、右側の肩周辺の組織への栄養供給を改善し、自然治癒力を高めることにもつながります。
2.1.2 関節可動域の改善とストレッチ
右側の肩の痛みが慢性化すると、肩関節の動きが悪くなり、可動域が制限されてしまうことがよくあります。これは、筋肉の硬直や関節包の拘縮などが原因で起こります。
整骨院では、まず硬くなった筋肉や関節包を特定し、専門的な手技によって柔軟性を取り戻すためのアプローチを行います。これにより、右腕を上げにくい、後ろに回しにくいといった動作の制限を改善し、日常生活での不便さを解消していきます。
施術においては、患者様一人ひとりの状態に合わせたストレッチを丁寧に行います。無理のない範囲で関節の動きを広げ、筋肉の柔軟性を高めることで、右側の肩の負担を軽減し、痛みの再発予防にもつながります。
これらの施術は、血行を促進し、筋肉の回復を助けるだけでなく、正しい姿勢を維持するための筋肉のバランスを整える効果も期待できます。
3. 右側の肩の痛みを根本から改善する整骨院の施術ステップ
右側の肩の痛みは、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。整骨院では、その場しのぎの対処ではなく、痛みの根本原因にアプローチし、再発しにくい体づくりを目指した施術を提供しています。ここでは、右側の肩の痛みを根本から改善するための施術ステップを具体的にご紹介いたします。
3.1 ステップ1 初回カウンセリングと検査
整骨院での施術は、まず患者様の状態を正確に把握することから始まります。右側の肩の痛みがどこから来ているのか、どのような性質の痛みなのかを徹底的に調べていきます。
| 項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 目的 | 右側の肩の痛みの原因を特定し、現在の状態を詳細に把握することです。患者様の生活習慣や既往歴なども考慮し、総合的な視点から痛みの背景を探ります。 |
| 具体的な流れ | まずは詳細な問診を行い、痛みがいつから始まったのか、どのような時に痛みを感じるのか、過去の怪我や病歴、日頃の姿勢や仕事内容、睡眠状況などをお伺いします。次に、視診で姿勢や体のバランス、肩の位置などを確認し、触診で右肩周辺の筋肉の緊張具合や圧痛点、関節の動きを丁寧にチェックします。さらに、腕を上げたり回したりする動作検査を通して、肩の可動域や痛みが出る特定の動作を特定していきます。これらの検査結果をもとに、患者様の右肩の痛みの原因を明確にし、今後の施術計画をご提案いたします。 |
3.2 ステップ2 痛みの緩和を目的とした施術
初回カウンセリングと検査で痛みの原因が特定できたら、まずは現在のつらい痛みを和らげるための施術を行います。痛みを軽減することで、その後の根本改善に向けた施術へとスムーズに進むことができます。
| 項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 目的 | 現在感じている右側の肩の痛みを速やかに緩和し、日常生活の負担を軽減することです。 |
| 具体的な流れ | 手技療法を中心に、硬くなった筋肉の緊張をほぐし、血行を促進することで痛みの軽減を図ります。特に、痛みの原因となっている深部の筋肉や筋膜にアプローチする筋膜リリースや、痛みの引き金となっている特定のポイントを刺激するトリガーポイント療法を組み合わせることで、効率的に痛みを和らげます。また、関節の動きが悪くなっている場合には、関節モビライゼーションと呼ばれる手技で、関節の可動域を広げ、動きをスムーズにしていきます。患者様の症状や痛みの程度に応じて、温熱療法や電気療法なども併用し、痛みの緩和を最大限に高めます。 |
3.3 ステップ3 根本改善と再発予防のための骨格矯正
痛みが緩和されたら、次に痛みの根本原因となっている体の歪みを整え、再発を防ぐための骨格矯正を行います。右肩の痛みは、肩だけでなく全身のバランスの崩れから来ていることが多いため、全身の骨格を調整することが重要です。
| 項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 目的 | 右側の肩の痛みの根本原因となっている体の歪みを整え、症状の再発を予防することです。 |
| 具体的な流れ | 骨盤や背骨、肩甲骨など、全身の骨格の歪みを丁寧にチェックし、手技によって正しい位置へと調整していきます。特に、右側の肩の痛みに関連が深いとされる猫背や巻き肩といった姿勢の崩れは、肩関節に過度な負担をかける原因となります。骨格矯正を通じて、これらの歪みを改善し、体全体のバランスを整えることで、肩への負担を軽減します。また、弱っている筋肉があればその機能を高めるためのアプローチを行い、硬くなっている筋肉には柔軟性を取り戻すための施術を加えることで、筋肉のバランスも調整していきます。これにより、正しい姿勢を維持しやすくなり、右肩への負担が軽減され、痛みが再発しにくい体へと導きます。 |
3.4 ステップ4 セルフケア指導と生活習慣のアドバイス
施術で改善された状態を維持し、再発を防ぐためには、ご自宅でのセルフケアや生活習慣の見直しが不可欠です。整骨院では、患者様一人ひとりに合わせた具体的なアドバイスを行います。
| 項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 目的 | 施術効果を維持し、右側の肩の痛みの再発を長期的に予防するための知識と実践方法を身につけていただくことです。 |
| 具体的な流れ | ご自宅で簡単に実践できるストレッチや体操の方法を丁寧に指導いたします。特に、右肩周辺の筋肉の柔軟性を保つためのストレッチや、姿勢を支える体幹の筋肉を強化する体操などが中心となります。また、日頃の生活習慣を見直すための具体的なアドバイスも行います。例えば、デスクワーク時の正しい姿勢や、スマートフォン操作時の注意点、ご自身の体に合った寝具の選び方や正しい寝姿勢の習慣化などです。重い荷物の持ち方や、日常生活での体の使い方についても、右肩に負担をかけないような工夫をお伝えします。さらに、栄養バランスの取れた食事や十分な睡眠の重要性についても触れ、全身の健康状態を良好に保つことの重要性をお伝えします。これらのセルフケアや生活習慣の改善を継続することで、施術で得られた効果を最大限に引き出し、右肩の痛みから解放された状態を長く維持することを目指します。今後の通院頻度についても、患者様の回復状況やライフスタイルに合わせて最適なプランをご提案いたします。 |
4. 右側の肩の痛みから解放されるための生活習慣の改善
整骨院での施術と並行して、日々の生活習慣を見直すことは、右側の肩の痛みを根本から改善し、再発を防ぐ上で非常に重要です。体の使い方や環境を少し変えるだけで、肩への負担を大きく軽減することができます。
4.1 デスクワーク環境の見直し
長時間のデスクワークは、右側の肩に大きな負担をかけ、痛みの原因となることが少なくありません。日々の作業環境を見直すことで、肩への負担を軽減し、痛みの改善につなげることができます。
4.1.1 モニターの位置と目線
モニターは、画面の上端が目線と同じか、やや下になるように調整してください。また、モニターとの距離は腕を伸ばしたときに指先が届く程度が理想的です。これにより、首が前に突き出す姿勢や、右側の肩が前に巻き込む姿勢を防ぐことができます。
4.1.2 椅子の選び方と正しい座り方
背もたれが高く、ランバーサポート(腰のサポート)がある椅子を選び、深く腰掛けるようにしましょう。足の裏が床にしっかりとつき、膝の角度が90度になるのが理想的な座り方です。右側の肩への負担を減らすためには、椅子の肘掛けを適切に使い、腕の重さを支えることも効果的です。
4.1.3 キーボードとマウスの配置
キーボードとマウスは、腕や右側の肩に無理な力がかからない位置に配置してください。肘の角度が90度から100度になるように調整し、手首をまっすぐに保つことが重要です。リストレストの活用も検討してみましょう。
4.1.4 定期的な休憩とストレッチ
1時間に一度は休憩を取り、席を立って軽く体を動かしましょう。右側の肩や首、肩甲骨周りの簡単なストレッチを行うことで、血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。
4.2 正しい寝姿勢の習慣化
寝ている間の姿勢は、右側の肩の痛みに大きく影響します。質の良い睡眠をとりながら、肩への負担を最小限に抑える寝姿勢を習慣化することが大切です。
4.2.1 適切な枕の選び方と高さ
枕は、仰向けに寝たときに首のカーブを自然に保ち、横向きに寝たときに頭から首、背骨までが一直線になる高さが理想的です。高すぎたり低すぎたりする枕は、右側の肩や首に負担をかける原因となります。素材も、頭や首にフィットするものが良いでしょう。
4.2.2 マットレスの硬さと体圧分散
マットレスは、体圧を適切に分散し、体のS字カーブをサポートする硬さが求められます。柔らかすぎるマットレスは体が沈み込み、硬すぎるマットレスは特定の部位に圧力が集中しやすくなります。右側の肩への負担を軽減するためには、寝返りを打ちやすい適度な反発力も重要です。
4.2.3 右側の肩に負担をかけない寝方
仰向けで寝る場合は、膝の下にクッションを入れると腰の負担が軽減され、全身がリラックスしやすくなります。横向きで寝る場合は、右側の肩を下にして寝ることを避け、左側を下にして寝るか、抱き枕などを活用して肩への圧迫を避ける工夫をしましょう。
4.3 肩に負担をかけない運動習慣
適切な運動習慣は、右側の肩の痛みを和らげ、再発を防ぐために非常に重要です。しかし、無理な運動はかえって痛みを悪化させる可能性があるため、注意が必要です。
4.3.1 ウォーミングアップとクールダウンの徹底
運動前には必ずウォーミングアップを行い、筋肉を温めて関節の可動域を広げましょう。運動後にはクールダウンとして軽いストレッチを行い、筋肉の緊張をほぐすことが、右側の肩の筋肉の疲労回復を促します。
4.3.2 肩甲骨周りのストレッチ
肩甲骨の動きが悪いと、右側の肩に負担がかかりやすくなります。肩甲骨を意識的に動かすストレッチを日常生活に取り入れましょう。例えば、両腕を大きく回したり、肩甲骨を寄せたり離したりする運動が効果的です。
4.3.3 インナーマッスルの強化
肩関節の安定には、深層にあるインナーマッスルが重要です。軽い負荷でゆっくりと行うトレーニングで、右側の肩を支えるインナーマッスルを強化しましょう。専門家のアドバイスを受けながら、適切な方法で行うことをおすすめします。
以下に、右側の肩の痛みに配慮した運動のポイントをまとめました。
| 運動の種類 | 具体的なポイント | 右側の肩への効果 |
|---|---|---|
| 肩甲骨ストレッチ | 両腕を前後に大きく回す、肩甲骨を寄せる・離す運動をゆっくりと行う。 | 肩甲骨の可動域を広げ、右側の肩の負担を軽減します。 |
| 首のストレッチ | 首をゆっくりと左右に傾ける、前後左右に回す(痛みがない範囲で)。 | 首から右側の肩にかけての筋肉の緊張を和らげます。 |
| 体幹トレーニング | プランクやドローインなど、腹筋と背筋をバランス良く鍛える。 | 体の軸を安定させ、右側の肩への負担を間接的に軽減します。 |
| 軽い有酸素運動 | ウォーキングや水中ウォーキングなど、全身を動かす運動。 | 血行を促進し、右側の肩の回復をサポートします。 |
4.4 栄養バランスの取れた食事
体は食べたもので作られています。右側の肩の痛みからの回復や、健康な状態を維持するためには、栄養バランスの取れた食事が不可欠です。
4.4.1 炎症を抑える栄養素
炎症性の痛みを抱えている場合は、炎症を抑える効果が期待できる栄養素を積極的に摂取しましょう。特に、青魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸(DHAやEPA)は、体内の炎症反応を抑制する働きがあると言われています。
4.4.2 筋肉や関節の修復を促す栄養素
右側の肩の筋肉や関節の修復には、良質なタンパク質、ビタミンC、ビタミンD、カルシウム、マグネシウムなどが重要です。肉、魚、卵、大豆製品からタンパク質を、野菜や果物からビタミンCを、きのこ類や乳製品からビタミンDやカルシウムを摂取するように心がけましょう。
4.4.3 水分補給の重要性
体内の水分が不足すると、血液の循環が悪くなり、筋肉の柔軟性も低下しやすくなります。これにより、右側の肩の筋肉がこわばり、痛みを引き起こす可能性もあります。一日を通してこまめに水分を補給し、体の機能を良好に保ちましょう。
以下に、右側の肩の回復をサポートする栄養素と食品例をまとめました。
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 筋肉や骨、関節の主要な構成成分となり、組織の修復を促進します。 | 肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品 |
| オメガ3脂肪酸 | 炎症を抑制し、血行を改善する効果が期待されます。 | サバ、イワシ、サンマなどの青魚、亜麻仁油、えごま油 |
| ビタミンC | コラーゲンの生成を助け、軟骨や腱の健康維持に貢献します。 | パプリカ、ブロッコリー、柑橘類、イチゴ |
| ビタミンD | カルシウムの吸収を助け、骨の健康を保ちます。 | きのこ類、魚介類(特に鮭)、卵 |
| カルシウム | 骨や歯の主要な成分であり、筋肉の収縮にも関与します。 | 牛乳、チーズ、ヨーグルト、小魚、小松菜 |
| マグネシウム | 筋肉の働きをサポートし、神経伝達にも関わります。 | 海藻類、ナッツ類、大豆製品、ほうれん草 |
5. 右側の肩の痛みを整骨院で治療する際の注意点
右側の肩の痛みを改善するために整骨院での治療を始める際、効果を最大限に引き出し、安心して施術を受けていただくためにはいくつかの注意点があります。これらのポイントを押さえることで、よりスムーズに、そして着実に症状の改善を目指すことができるでしょう。
5.1 無理のない通院計画を立てる
整骨院での治療は、一度の施術で全てが解決するわけではありません。症状の根本改善には、継続的なアプローチが不可欠です。そのため、ご自身の生活スタイルや症状の進行度合いに合わせて、無理のない通院計画を立てることが非常に大切になります。
初回のカウンセリング時に、施術者としっかりと話し合い、具体的な通院頻度や期間について相談しましょう。仕事や家庭の事情、体力的な負担などを考慮し、長期的に継続できる計画を立てることが、結果として右側の肩の痛みを着実に和らげる道となります。
| 通院計画のポイント | 詳細 |
|---|---|
| 生活スタイルとの両立 | 仕事や家事、プライベートの予定を考慮し、通院が負担にならない曜日や時間帯を選びましょう。 |
| 症状の段階に応じた調整 | 痛みが強い急性期と、症状が落ち着いてきた慢性期では、適切な通院頻度が異なります。施術者と相談し、都度見直してください。 |
| 目標設定の共有 | いつまでにどのような状態を目指すのか、具体的な目標を施術者と共有することで、計画のモチベーション維持にもつながります。 |
無理な通院は、途中で挫折してしまう原因にもなりかねません。ご自身のペースで通い続けられる計画を立てることが、右側の肩の痛みを根本から改善するための第一歩です。
5.2 治療中の違和感はすぐに伝える
整骨院での施術は、お客様一人ひとりの体の状態に合わせて行われます。しかし、施術中に「いつもと違う痛みがある」「特定の動作で不快感がある」「少し強いと感じる」といった違和感を覚えることがあるかもしれません。
そのような時は、決して我慢せず、すぐに施術者に伝えてください。施術者は、お客様からのフィードバックに基づいて、施術の強さや方法を調整し、より効果的で安全なアプローチを行うことができます。コミュニケーションは、施術の効果を高める上で非常に重要です。
| 伝えるべきこと | 伝えることで得られるメリット |
|---|---|
| 施術中の痛みや不快感 | 施術の強さや角度が調整され、体に合った安全な施術を受けられます。 |
| 施術前後の体調の変化 | 施術の効果を正確に評価し、次回の施術計画に反映させることができます。 |
| 日常生活での変化 | 痛みの原因や再発予防のためのアドバイスが、より具体的になります。 |
「こんなことを言っても良いのだろうか」と遠慮する必要はありません。安心して施術を受けるためにも、気になることは何でも伝えるように心がけてください。それが、右側の肩の痛みの早期改善と、施術者との信頼関係構築につながります。
6. まとめ
右側の肩の痛みは、日々の生活習慣や体の使い方、さらには加齢など、様々な要因が複雑に絡み合って生じることがあります。整骨院では、丁寧な問診と検査を通じて痛みの根本原因を特定し、筋膜リリースや骨格矯正、関節可動域の改善といった専門的なアプローチで、一時的な痛みの緩和だけでなく、再発しにくい体づくりを目指します。また、セルフケア指導や生活習慣のアドバイスも行い、お客様ご自身で健康を維持できるようサポートいたします。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。
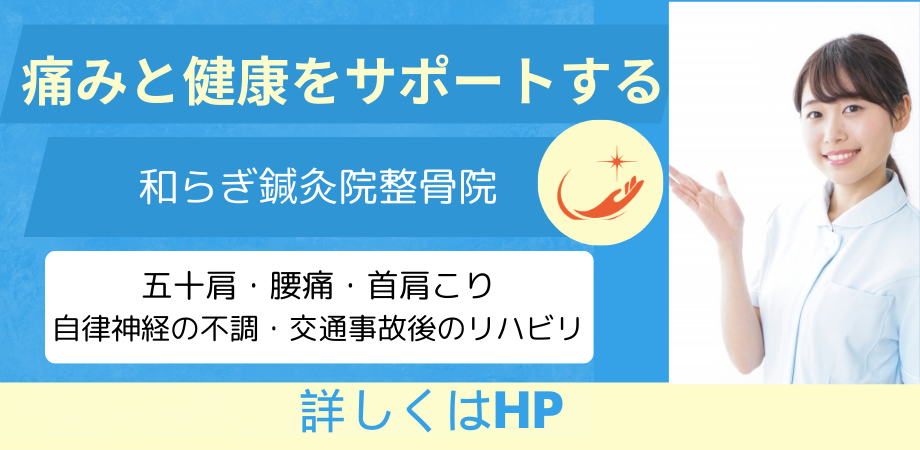














コメントを残す